お客様サポートダイヤル
【香川】 0120-056-873
0120-056-873
【徳島】 0120-3158-94
0120-3158-94
早朝・深夜も専任スタッフが
迅速に対応いたします
1時間以内にお迎えに伺います(一部地域を除く)
弊社の葬儀コンシェルジュがご状況を確認させていただき、今必要な⼿続き等をご案内させていただきます。

 ご危篤
ご危篤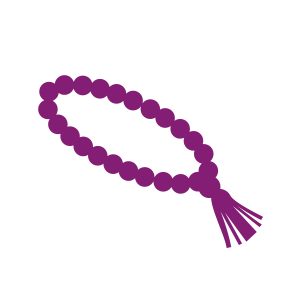 ご逝去
ご逝去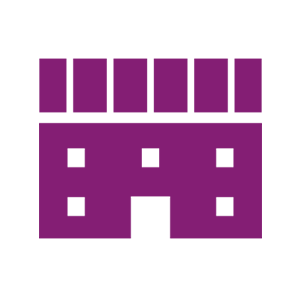 葬儀社⼿配
葬儀社⼿配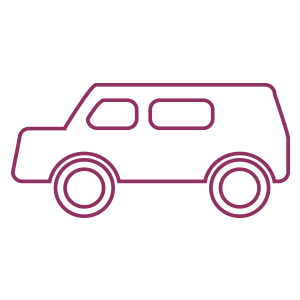 搬送
搬送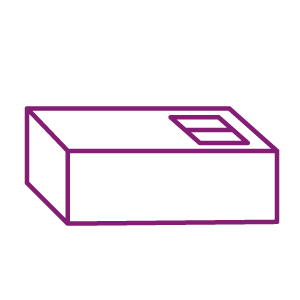 安置
安置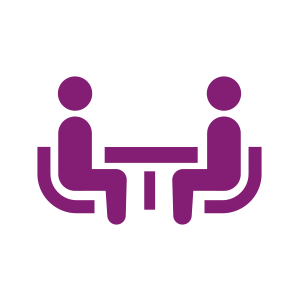 葬儀打合せ
葬儀打合せ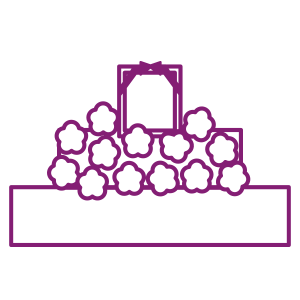 葬儀準備
葬儀準備死亡宣告を受けた後に、病院から早く移動するように⾔われたのですが・・。

病院では患者の死亡後、医師が死亡診断書を作成し、看護師やスタッフが遺体の処置を⾏います。病院によって異なりますが、通常はなるべく早く病院を離れるように促されることもあります。
まずは、家族葬の花⽔⽊にご連絡ください。迅速にお迎えにあがります。
ご希望の搬送先をお電話の際にお伝えください。
⾃宅療養中の家族が亡くなりました。覚悟はしていましたが、少し動揺しています・・。

遺体を動かしたり、慌てて救急⾞を呼ぶことがないよう気をつけましょう。まずは、かかりつけの医師を呼び死亡診断書を発⾏してもらいましょう。
かかりつけの医師にご連絡後、家族葬の花⽔⽊までご連絡ください。
今後のことをしっかりサポートさせていただきます。
家族が外出先で亡くなり、警察署で安置していると連絡がありました。

病死や⾃然死以外の場合、検視が⾏われることになります。検視が完了すると、遺体は家族の元に引き渡されることになります。検視には数⽇〜場合によっては1カ⽉程度かかる場合もあります。
家族葬の花⽔⽊にまず連絡いただき、ご状況やご要望をお聞かせいただければ、適切なアドバイスを差し上げます。
検視の期間が分からない場合でも、お気軽にご連絡ください。
早朝・深夜も専任スタッフが
迅速に対応いたします
親族が亡くなった場合、どのような⼿続きが必要なのでしょうか?
まずは家族葬の花⽔⽊までご連絡ください。弊社の葬儀コンシェルジュが今後の流れや必要な⼿続きなどご案内いたします。葬儀に関する不安を解消するために、事前相談やお⾒積りのみのお問い合わせも歓迎しております。お客様の気持ちに寄り添い、より詳細かつ丁寧な対応を提供させていただきます。
葬儀⼿配に関して事前の予約は必要でしょうか?
葬儀を⼿配する際、事前の予約は必要ありません。突然のご逝去にも迅速に対応します。私たちは24時間365⽇、葬儀専⾨のコンシェルジュが対応いたします。突然の場合でも、病院や施設からお迎えの⼿配や遺体の安置、葬儀や⽕葬場の⼿配を迅速に⾏います。深夜や早朝でも、いつでもお電話ください。
【香川】0120-056-873
【徳島】0120-3158-94
⾃宅に安置できない場合は、どうしたらいいですか?
家族葬の花⽔⽊では安置施設をご⽤意しておりますので、安⼼してください。病院や介護施設から、「早急に葬儀社へ引取りを依頼してください」と⾔われるケースが多くあります。当社にご連絡いただければ、最短60分でスタッフがご指定の場所へお迎えに伺います。お電話の際に、安置場所としては家族葬の花⽔⽊の斎場を希望とお伝えください。